縫殿神社の秋祭り

裁縫の神様、本殿の絵馬は見事
応神(おうじん)天皇のころに、呉の国(今の中国)から兄媛(えひめ)、弟媛(おとひめ)、呉織(くれはとり)、穴織(あなはとり)の4人の媛が織物、縫物の進んだ技術を日本に伝えるために招かれました。この中の兄媛は宗像神の求めでこの地に残り、中国の高度な染色、機織り、裁縫の技術を広めたと言われています。
祭神は、この4人の媛と応神天皇、神功(じんぐう)天皇、大歳(おおとし)神で、この神社は日本最初の裁縫の神様であり、この地はデザイン、ファッションの発祥の地と言えます。
この神社には、永享(えいきょう)12年(1440年)につくられた梵鐘(ぼんしょう)(県指定有形文化財、宗像大社神宝館に展示)、南北朝時代の大般若経(だいはんにゃきょう)600巻や江戸時代中期ごろの三十六歌仙絵扁額をはじめとする絵馬があります。
基本情報
- 場所
〒811-3522 福津市奴山813番地 - 問い合わせ
地域振興部 地域振興課
電話番号:0940-62-5014
イベント情報
秋季大祭

五穀豊穣を願い、お神輿が練り歩く
祭神は大歳(おおとし)神・応神天皇・神功皇后(じんぐうこうごう)・工女兄媛(えひめ)・弟媛(おとひめ)・呉識(くれはとり)・穴識(あなはとり)です。言い伝えによると、神功皇后が新羅に出兵する際に、船の帆を縫ったということです。永亨12年に宗像大宮司氏俊(むなかただいぐうじうじとし)が寄進した梵鐘(高さ約81センチメートル、口径約47センチメートル、厚さ約5センチメートル)があり、福岡県指定文化財(工芸品)に指定されています。毎年9月13日には、五穀豊穣・家内安全を祈願して、御神幸行列が、神社から奴山川で禊をしたのち、地区内を練り歩きます。祭神が女性神であることから、御神輿の舁き手には、未婚の男子が選ばれていました。
フォトガイド



交通アクセス
県道528号から入る
駐車台数 なし
このページの作成部署
経済産業部 観光振興課 観光振興係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所別館2階
電話番号:0940-62-5014
ファクス番号:0940-43-9003
メールでのお問い合わせはこちら
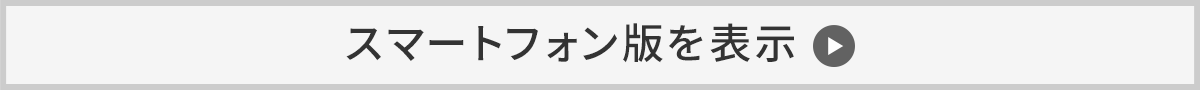






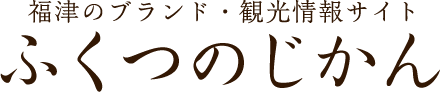










更新日:2020年02月27日