手光立花木遺跡
市内初! 穴の中から縄文土器を発見!!
遺跡名 : 手光立花木遺跡(てびかたちばなぎいせき)
所在地 : 福津市手光
調査期間 : 令和5年4月20日~同年7月24日
調査面積 : 853平方メートル
遺跡の種別: 集落遺跡
遺跡の概要:
手光立花木遺跡は福津消防署建設に伴い発掘調査を実施した縄文時代から平安時代までの集落遺跡です。
宮地岳より南に派生する丘陵上に位置し、標高は約17mです。調査地の南側には手光今川が西流し、同河川周辺の沖積地平野は田畑として利用されています。見つかった遺構は竪穴建物3軒、掘立柱建物2棟、土坑6基、溝1条、小穴多数です。出土した遺物は縄文土器、弥生土器、土師器、須恵器、石器、鉄滓、フイゴ羽口などが出土しています。古墳時代の資料はないものの、縄文時代後期初頭から奈良・平安時代まで断続的に集落として営まれていたことが分かってきています。
特に注目されるのは、縄文時代後期初頭~前葉の縄文土器です。これまで福津市内では遺構に伴って縄文土器が出土した事例はありませんでしたが、今回の調査で初めて遺構に伴う縄文土器を確認することができました。これらの縄文土器は熊本県の阿高貝塚で見つかっている阿高式土器と類似しており、人と物の移動が当時から行われていたことを示しています。弥生時代早期~前期の土器は、平面プランが長楕円形の竪穴建物でまとまって見つかっています。これらの土器も市内における弥生文化成立期の様子を解き明かしていく上で大変貴重な資料です。奈良・平安時代の掘立柱建物は南北に主軸を取った建物で、周辺からは鉄滓などの鍛冶関係の遺物、焼けた土が入れられた土坑などが見つかっています。

見つかった縄文土器

弥生時代早期~前期の竪穴建物
このページの作成部署
- より良いホームページにするために皆さんのご意見をお聞かせください
-












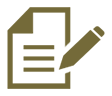





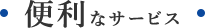






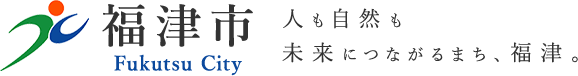







更新日:2024年11月20日