国民健康保険税
国民健康保険税について
国民健康保険は、病気やケガをしたときに安心して医療が受けられるように加入者が保険税を出し合い、お互いを助け合う制度です。国民健康保険税は、この制度を支える貴重な財源です。
保険税の決まり方
国民健康保険税は、医療保険分・後期高齢者支援金分・介護納付金分を合計した金額が1年間(4月~翌年3月)の税額です。加入者の年齢によって、次のように課税されます。
- 40歳未満と65歳以上の人は、医療保険分と後期高齢者支援金分
- 40歳以上65歳未満の人は、医療保険分と後期高齢者支援金分と介護納付金分
保険税は、加入の手続きをしたときからではなく、保険の資格が始まったときまで、さかのぼって課税します。
年度途中で加入・脱退した場合は、年税額を月割して税額を算出します。
国民健康保険税の納税通知書は、毎年6月中旬頃発送します。
納税義務者
国民健康保険税は世帯主に課税され、世帯主が納税義務者となります。
世帯主が国民健康保険の加入者ではない(世帯員のみ加入者である)場合も、世帯分の保険税として世帯主に課税されます。
平成30年度からの国民健康保険制度
平成30年度から、都道府県が算定した標準保険税率をもとに市区町村が保険税率(額)を決定する形に変更されました。
令和7年度の保険税率等を改定しました
| 賦課年度 | 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 医療保険分 | 所得割 | 7.80% | 8.00% | -0.20% |
| 均等割 | 25,000円 | 26,700円 | -1,700円 | |
| 平等割 | 25,000円 | 26,700円 | -1,700円 | |
| 後期高齢者支援金分 | 所得割 | 2.50% | 2.50% | ー |
| 均等割 | 9,000円 | 8,000円 | +1,000円 | |
| 平等割 | 9,000円 | 8,000円 | +1,000円 | |
| 介護納付金分 | 所得割 | 2.20% | 2.20% | ー |
| 均等割 | 13,500円 | 13,100円 | +400円 | |
| 平等割 | ー | ー | ー | |
保険税の算出方法(令和7年度)
国民健康保険税は、下記のとおり【1】医療保険分【2】後期高齢者支援金分【3】介護納付金分(40歳以上65歳未満の人に課税)について、所得割額、均等割額、平等割額を合算し、世帯ごとに算出します。なお、所得割額は所得がある加入者のみが対象となります。
※令和7年度に改定した税率等を赤字で示しています。
【1】医療保険分
加入者の医療費のうち、医療機関の窓口で支払う自己負担金額を除いた福津市が負担する保険給付額に充てられます。
- 所得割額 (前年の総所得金額等(注釈1)-基礎控除43万円(注釈2))×7.80%
- 均等割額 被保険者数(加入者数)×25,000円
- 平等割額 1世帯あたり 25,000円
【2】後期高齢者支援金分
75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度への支援金に充てられます。
- 所得割額 (前年の総所得金額等(注釈1)-基礎控除43万円(注釈2))×2.50%
- 均等割額 被保険者数(加入者数)×9,000円
- 平等割額 1世帯あたり 9,000円
【3】介護納付金分(40歳以上65歳未満の人に課税)
40歳以上65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者)に係る介護保険への納付金に充てられます。
- 所得割額 (前年の総所得金額等(注釈1)-基礎控除43万円(注釈2))×2.20%
- 均等割額 被保険者数(加入者数)×13,500円
- 平等割額 ありません
- (注釈1)総所得金額等は、前年の総所得金額に分離課税の所得金額や山林所得などを加算した金額です。例えば、給与所得のみの場合は、源泉徴収票の給与所得控除後の金額や、確定申告書の所得金額の合計欄の金額が総所得金額等となります。詳しくはお尋ねください。
- (注釈2)控除されるのは基礎控除のみです。所得税や住民税で控除される所得控除等は対象外です。
年税額の最高限度額
- 1世帯当たりの医療保険分…660,000円
- 1世帯当たりの後期高齢者支援金分…260,000円
- 1世帯当たりの介護保険分…170,000円
令和7年度国保税試算シート (PDFファイル: 140.7KB)
保険税の免除・軽減について
産前産後の期間に係る免除(要申請)
令和6年1月から、出産(予定を含む)の前後の期間に係る妊産婦の国民健康保険税を免除する制度が施行されました。
対象者
下記のいずれにも該当する人
- 妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む)であること
- 令和5年11月1日以降の出産であること
免除の概要
対象者の所得割と均等割が免除
免除対象期間
- 単胎の場合 出産(予定)月と前1カ月と後2カ月の計4カ月
- 多胎の場合 前3カ月と後2カ月の計6カ月
申請に必要なもの
- 国民健康保険資格確認書等
- 母子手帳
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
※申請は出産予定日の6カ月前から可能です。
【参考】免除対象期間 ※太枠で囲まれた部分

【参考】1年間の保険税 (例)大人2人・新生児1人の世帯の場合

非自発的な理由で失業した方の軽減(要申請)
倒産・解雇・雇い止めなどの特定の理由で離職された方(非自発的失業者)は、申請することにより国民健康保険税が軽減されます。
対象者
雇用保険受給資格者証の記載事項が次のすべてに該当する人
- 離職時の年齢が65歳未満
- 対象者離職理由コードが以下の場合
11、12、21、22、31、32(特定受給資格者)
23、33、34(特定理由離職者)
軽減措置の概要
前年の給与所得を30/100として計算
※軽減措置の対象となるのは離職した本人のみです。
軽減適用年度
離職日の翌日の属する年度とその翌年度
申請に必要なもの
- 国民健康保険資格確認書等
- 雇用保険受給資格者証
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
一定所得以下の世帯の軽減(申請不要)
世帯主(世帯主が加入者でない場合も含む)およびその世帯の加入者の総所得金額が次の基準以下の場合は、均等割額と平等割額が軽減されます。この判定のため、収入のなかった人、非課税の収入(障害年金、遺族年金)の人も申告が必要になることがあります。
|
軽減割合 |
軽減対象となる所得の基準 |
|---|---|
|
7割 |
43万円+(給与所得者等の数(注釈2)-1)×10万円以下 |
|
5割 |
43万円+30.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数(注釈1)+(給与所得者等の数(注釈2)-1)×10万円以下 |
|
2割 |
43万円+56万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数(注釈1)+(給与所得者等の数(注釈2)-1)×10万円以下 |
(注釈1)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人です。
(注釈2)一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。
未就学児の均等割の軽減(申請不要)
令和4年度から、子育て世代の経済的負担軽減を図るため国民健康保険に加入している未就学児の均等割額の2分の1を減額しています。
世帯の所得が一定以下で軽減が適用される世帯の未就学児の均等割額については、当該軽減後の均等割額をさらに減額しています。
| 軽減前税額 | 軽減額 | 軽減後税額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7割軽減 | 医療保険分 | 7,500円 | 3,750円 | 3,750円 | ||
| 後期高齢者支援金分 | 2,700円 | 1,350円 | 1,350円 | |||
| 合計 | 10,200円 | 5,100円 | 5,100円 | |||
| 5割軽減 | 医療保険分 | 12,500円 | 6,250円 | 6,250円 | ||
| 後期高齢者支援金分 | 4,500円 | 2,250円 | 2,250円 | |||
| 合計 | 17,000円 | 8,500円 | 8,500円 | |||
| 2割軽減 | 医療保険分 | 20,000円 | 10,000円 | 10,000円 | ||
| 後期高齢者支援金分 | 7,200円 | 3,600円 | 3,600円 | |||
| 合計 | 27,200円 | 13,600円 | 13,600円 | |||
| 軽減なし | 医療保険分 | 25,000円 | 12,500円 | 12,500円 | ||
| 後期高齢者支援金分 | 9,000円 | 4,500円 | 4,500円 | |||
| 合計 | 34,000円 | 17,000円 | 17,000円 | |||
後期高齢者医療保険への移行に伴う軽減(申請不要)
75歳になった人(一定の障害認定を受け申請をした65歳以上の人を含む)は、後期高齢者医療制度に移行することになります。それに伴って国民健康保険に加入している人の国保税の負担が急激に増えることがないように、以下の世帯は次のような軽減制度があります。
一定所得以下の世帯の軽減
後期高齢者医療制度に移行する前に国保税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、これまでと同じ軽減を受けることができます。
平等割の軽減
世帯主または世帯員が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、国民健康保険の被保険者が1人だけとなった世帯(特定世帯)は、5年間平等割が2分の1軽減されます。その後3年間は特定継続世帯として、平等割が4分の1軽減されます。
保険税の納期
| 普通徴収 | 期別 | 納期限 |
|---|---|---|
| 1期 | 令和7年6月30日 | |
| 2期 | 令和7年7月31日 | |
| 3期 | 令和7年9月1日 | |
| 4期 | 令和7年9月30日 | |
| 5期 | 令和7年10月31日 | |
| 6期 | 令和7年12月1日 | |
| 7期 | 令和8年1月5日 | |
| 8期 | 令和8年2月2日 | |
| 9期 | 令和8年3月2日 | |
| 10期 | 令和8年3月31日 | |
|
特別徴収 (年金から天引き) |
月別 | 引落日 |
| 4月 | 令和7年4月15日 | |
| 6月 | 令和7年6月13日 | |
| 8月 | 令和7年8月15日 | |
| 10月 | 令和7年10月15日 | |
| 12月 | 令和7年12月15日 | |
| 2月 | 令和8年2月13日 |
納付書または口座振替の納期限は各月末日です。その日が金融機関の休業日の場合は翌営業日が納期限です。ただし、第7期の納期限は令和8年1月5日です。
年金天引きは支給される年金から保険税が徴収されます。偶数月の15日が金融機関の休業日の場合、年金は直前の営業日に支給されます。
特別徴収(年金からの天引き)について
世帯主が加入者で、その世帯の加入者の全員が65歳以上75歳未満であって、世帯主が次の条件に該当する場合は、特別徴収(年金からの天引き)となります。
- 年額18万円以上の年金受給者である
- 年金から介護保険料が特別徴収されている
- 介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金受給額(1回毎)の2分の1を超えない
なお、この特別徴収は、世帯主の申し出により普通徴収(口座振替)に変更することができます。納付書による納付には変更できません。申し出のあった月の2カ月先以降の年金からの特別徴収が中止され、口座振替に変更になります。
保険税の減免について
災害等により国保税の納付が困難になったときは、申請により国保税の減免を受けられる場合があります。なお、申請は納期限の7日前までに行う必要があります。詳しくはご相談ください。
災害による被害を受けた場合
世帯主または世帯員の所有する住宅または家財(償却資産)が、震災や火災等の災害によって、住宅の価格(当該年度における固定資産評価額)または家財の価格の30%以上の損害を受けた場合
著しく所得が減少した場合
世帯主または世帯員が傷病・失業(定年退職、自己都合による退職及び契約期間満了による解雇等を除く。)等の理由により、本年中の見込所得金額の合計額が前年中の合計所得金額と比較して著しく激減し、生活が著しく困難になった場合
生活保護の受給を開始した場合
生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受け、その受給を開始した場合
保険給付の制限を受ける場合
刑事施設等に収容または拘禁された場合
被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することで、その被扶養者(65歳以上75歳未満)が国民健康保険に加入する場合
被用者保険の被保険者が75歳(一定の障害認定を受け申請をした65歳以上の人を含む)になり、後期高齢者医療制度に移行することに伴って、65歳以上75歳未満の被用者保険の被扶養者(旧被扶養者)が新たに国民健康保険に加入する場合
このページの作成部署
市民生活部 保険年金医療課 保険年金係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8127
ファクス番号:0940-43-8154
メールでのお問い合わせはこちら
- より良いホームページにするために皆さんのご意見をお聞かせください
-












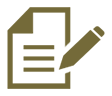

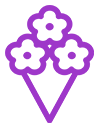



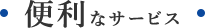






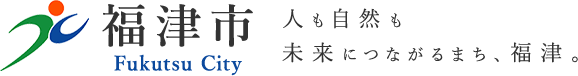







更新日:2025年04月16日