ごみの減量について
生活していく上で、さまざまな種類のごみが発生します。人によって排出する量は異なるでしょうが、年間を通して全くごみを出さないという人は、ほとんどいないのではないでしょうか。私たちの生活と密接に結びついている「ごみ」について考えることは、とても大切なことです。
フードドライブについて
令和6年11月1日より、うみがめ課の窓口でフードドライブを実施しています。
フードドライブとは、使いきれない未使用の食品を集め、必要とする方へ寄贈する活動のことです。
市では、皆さまから寄付いただいた食品を(一社)福岡県フードバンク協議会を通じ、支援を必要とする方へ食品を提供します。
家庭で使用予定のない食品があれば、ごみにするのではなく、寄付のご協力をお願いします。
●受付場所 うみがめ課窓口(市役所別館1階)
●受付時間 市役所開庁日 8:30~17:00
●受付方法 うみがめ課職員が受取りますので、職員へお声かけください。
■受付する食品
・常温で保存できるもの
・開封されていないもの、包装の破れがないもの
・賞味期限が明記され、賞味期限の残りが2カ月以上あるもの
(賞味期限表示義務のない米・砂糖・塩は、賞味期限の表示がなくても受付可)
■受付できない食品
・生鮮食品、保管に冷蔵・冷凍が必要なもの
・包装が破れているもの
・賞味期限が2カ月未満のもの
・食品表示、賞味期限表示がないもの
・アルコール飲料(料理酒を除く)
4Rについて
排出されるごみをゼロにすることは難しいかもしれませんが、減らすために次のようなことを意識することは、それほど難しいことではないはずです。「4R=リフューズ、リデュース、リユース、リサイクル」という言葉をぜひ覚えて欲しいと思います。
1、リフューズ(Refuse:発生抑制)
必要以上にものを買わないなど、ごみとなりそうなものは家庭に持ち込まないことが大切です。
2、リデュース(Reduce:排出抑制)
購入量や使用量を減らす、または長期に使用できるものを選ぶなど、なるべく自分のものをごみにしないことが大切です。
3、リユース(Reuse:再使用)
一度使用したものをすぐに捨てて新しいものを使用するのではなく、繰り返し使用することが大切です。
4、リサイクル(Recycle:再資源化)
なるべく資源として再利用するために、ごみを適切に分別することが大切です。
家庭から排出される燃やすごみ袋の中身の調査結果

上のグラフは、古賀清掃工場で毎年度行われている、家庭から排出される燃やすごみ袋の中身の調査結果(福津市、古賀市、新宮町)です。福津市が独自に行っている調査でも、おおむね同じような結果が出ています(前回は平成29年度に実施。次回は令和4年度実施予定)。この結果から、ごみの減量を行うためのヒントが見えてきます。
ごみ減量に向けての提案
「平成30年度ごみの種類組成」の結果より
1、「紙・布類」の減量をするには古紙・古着回収倉庫を利用する。
2、プラマークが付いている「ビニール」や「合成樹脂(プラスチック)」の減量をするには分別収集の「プラ容器包 装・食品用トレイ」へ(プラスチックに関しては容器包装や食品用トレイに使われていたものに限ります)。
3、「竹」の減量をするには分別収集の「剪定くず・草等」、または剪定くず・草ステーションを利用する。
4、「厨芥類」の減量をするには、食べきれる量だけ作る、保存できるものは保存して後日食べる、使い切れる分の食材しか買わない、なるべく水をきる等の工夫を行う。
レシピサイト「クックパッド」内の「消費者庁のキッチン(公式ページ)」も参考にしてください。
消費者庁ホームページ
ごみをなるべく資源として活かせるようにする、ごみ自体をそもそもあまり出さないようにすることを心がけましょう。
「平成30年度ごみの3成分」の結果より
ごみの成分の半分近くが水分という結果です。水分が多いと…
1、水分が焼却の妨げになり、清掃工場で焼却する際に余分なエネルギーが必要となります。
2、水分を含んで重くなり、収集運搬する際に余分なエネルギーが必要となります。
3、水分を含んで膨張し、ごみの量(必要なごみ袋の数)が多くなります。
野菜の切りくず等はできるだけ水に濡らさずに捨てるようにしましょう。また、水分を含んだ生ごみ等を出す際には、ネットなどに入れて「最後のひと絞り」を行うようにしましょう。
このページの作成部署
市民共働部 うみがめ課 資源リサイクル係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所別館1階
電話番号:0940-62-5019
ファクス番号:0940-43-9005
メールでのお問い合わせはこちら
- より良いホームページにするために皆さんのご意見をお聞かせください
-












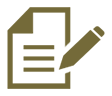





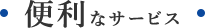






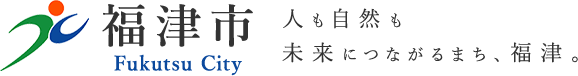







更新日:2024年11月01日