離乳食初期
離乳食開始時期のポイント
開始時期について
生後5~6カ月頃が適当ですが、お子さんの発達状況も確認しましょう。
発達や発育には個人差があるので、あせらずお子さんの様子を確認してから開始しましょう。
お子さんの発達「そろそろ離乳食開始」のサイン
- 首のすわりがしっかりしている
- 支えてあげると座れる
- 食べ物に興味をしめす
- スプーンなど口に入れても押し出そうとすることが少なくなる。(生後5~7カ月頃から舌で押し出そうとする反応が消えていきます)

開始時期は1日1回食から
開始時期は、離乳食を飲み込むこと、その舌ざわりや味に慣れることが目的です。
離乳食は1日1回あたえます。
母乳または育児用ミルクは、授乳のリズムに合わせて十分にあたえます。
まだまだ栄養は母乳や育児用ミルクが主です。(母乳をあたえている方は、ママの食事も大切です。)
あたえるタイミング
お子さんの機嫌の良い時間帯、何かあった時に病院に行ける午前中がおすすめです。
離乳食をあたえた後は、赤ちゃんの欲しがるだけ母乳や育児用ミルクをあたえましょう。
離乳食のすすめ方
10倍がゆからスタート
10倍がゆをなめらかにすりつぶしたものを少量(赤ちゃんスプーン1さじ)からスタートします。少しずつ量を増やしていきます。
野菜
10倍がゆに慣れてきて1週間くらいしたら、野菜をやわらかく茹でて、つぶしたなめらかなものを少量(赤ちゃんスプーン1さじ)から試していきます。最初はあくの少ない人参、じゃがいも、かぶなどがおすすめ。少しずついろいろな味を体験させましょう。
たんぱく質
おかゆ、野菜に慣れてきて少しずつ量も増えてきたら、熱湯で茹でたとうふや白身魚、固ゆで卵の卵黄を少量(赤ちゃんスプーン1/2さじ)から試していきます。
2回食へすすめるタイミング
生後7~8カ月頃が目安です。
離乳食を開始して1~2カ月過ぎ、おかゆ、野菜、たんぱく質と量も増えてきたら、2回食にしリズムを作っていきます。
形態は、お子さんの様子を見ながら、下の歯が生えてきたら、つぶしやすいものは、トロトロから少しずつ粗つぶしにアップしていきます。
食べられる食材も増えてきます。
注意事項!!
はちみつは、乳児ボツリヌス予防のために1歳過ぎるまではあたえないようにしましょう!!
果汁やイオン飲料、赤ちゃん用ジュースについて
赤ちゃんにとっての最適な栄養は母乳や育児用ミルクです。糖分の多い飲料は赤ちゃんにとって負担になります。あたえすぎないように注意しましょう。
離乳食づくりのきほんの「き」
赤ちゃんの発達に合わせて、飲み込みやすく、食べやすくつくってみましょう。
離乳食づくりのきほんの「き」(PDFファイル:364.7KB)
フリージングのポイント
新鮮な食材を使う。
栄養も鮮度も日に日に落ちていきます。新鮮なうちに調理、冷凍しましょう。
よく冷ましてから冷凍する。
冷凍庫内の雑菌の繁殖を防ぐため、よく冷ましてから冷凍しましょう。
空気に触れない様に密閉する。
味の劣化や酸化を防ぐため、密閉容器を使ったり、ラップに包んだものを冷凍用保存袋に入れたりしましょう。
1回に使う量に小分けする。
食べる分だけ解凍できるので、使い勝手が良く鮮度も保たれます。
解凍後は再び凍らせない。
味や栄養分が落ち、雑菌が繁殖する場合もあるので、1回使い切りを心がけましょう。
1週間から10日を目安に使い切る。
大人のメニューから取り分ける時のポイント!
取り分けのタイミングは、食事を作る過程で取り分けて、月齢に合わせた形態にしましょう。
1.まだ食べられない食材(油や脂っぽい食材)を入れる前に取り分け。
2.味付け(しょうゆ・塩・みそ等)をする前
食物アレルギーの考え方
食物アレルギーを心配して離乳食の開始時期を遅らせたり、自己判断で食材を除去するのは禁物。少量から試してみましょう。アレルギー体質の可能性がある場合は、まず医師に相談しましょう。
初めての食材は体調の良い時に試しましょう。
食物アレルギーの症状と対応策
・主な症状
じんましん・皮膚の発赤・かゆみ・嘔吐・下痢・腹痛・せき・ぜいぜい・呼吸困難 など
・対応策
症状が出た場合は、何を食べたかメモして医師に相談しましょう。
離乳食初期(5~6カ月頃)のレシピ
10倍がゆ
米から鍋で炊く
米から鍋で炊く作り方(PDFファイル:326.3KB)
炊いたご飯から作る
炊いたご飯からの作り方(PDFファイル:329.9KB)
炊飯器で一緒に炊く
炊飯器で一緒に炊く作り方(PDFファイル:314.8KB)
にんじんペースト
キャベツペースト
白身魚ペースト
「10倍がゆ」「野菜ペースト」「魚ペースト」の作り方を動画で紹介してますので、ぜひご覧ください。
このページの作成部署
こども家庭部 子育て世代包括支援課 保健指導係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-34-3352
ファクス番号:0940-42-6939
メールでのお問い合わせはこちら
- より良いホームページにするために皆さんのご意見をお聞かせください
-












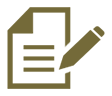

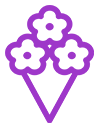



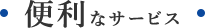






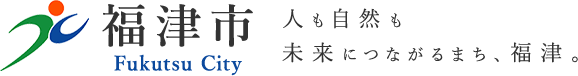







更新日:2024年03月28日